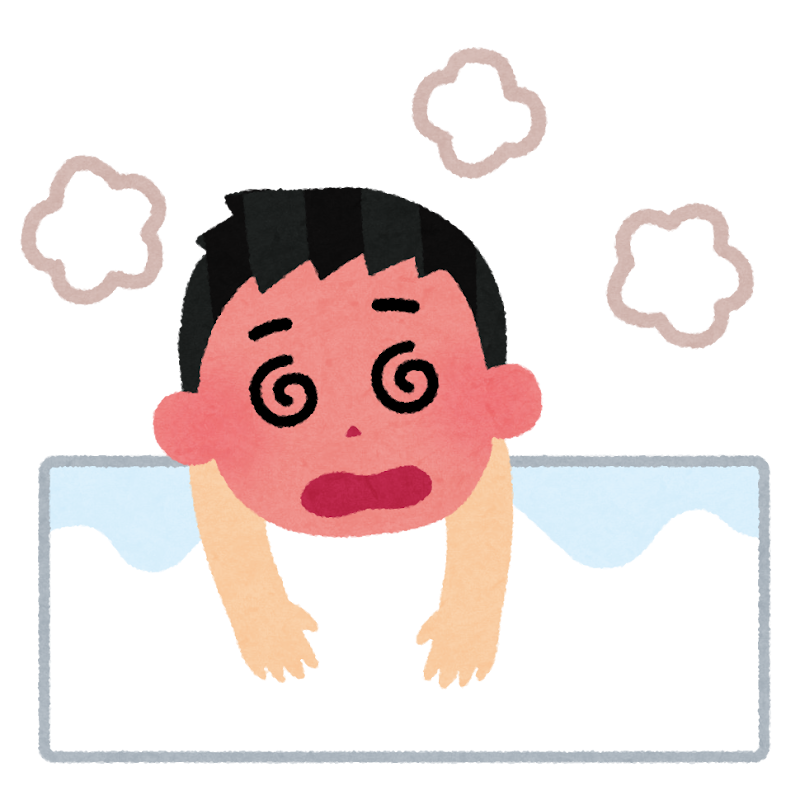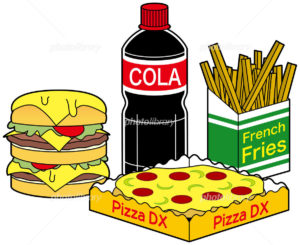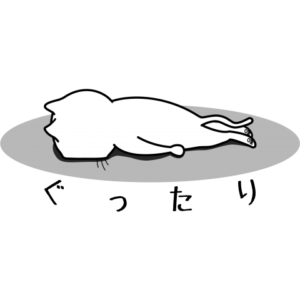春の過ごし方
春は気温の上下が激しく、体内のエネルギーが上下に揺さぶられます。エネルギーは上下に動きやすくなり、上へと上る傾向になります。一種ののぼせのようになり、めまいや頭痛、咳が多く出るようになります。もちろん気温差から風邪も引きやすくなります。
そのエネルギーの流れを止めてしまうのは好ましくありません。上にのぼってきたエネルギーを淀みなく、体外に流します。寒いので、マフラーを一生懸命巻きたくなるのですが、できるだけ薄い物にするか、止めるように頑張ってみましょう。
でもやり過ぎて風邪をひかないよう、注意してくださいね。

2023年03月05日
食べて治す腹痛
最近太ってしまい、食事をやや制限しながら過ごしていたのですが、
そのうち何だか食べられなくなって、下痢しました。
食べられない時には食べません。何か変なものを食べたのかなと思い、、
様子をみていました。大体なおったものの、1時間に1回程度生じる
痙攣のような腹痛が残りました。
昨日はうどんとおかゆだけ。今日はおかゆ。。。

この痛みはもしかしてグルタミン不足!と思い当たりました。
グルタミンは腸粘膜の栄養になるアミノ酸です。実は、学生の頃の長距離走で間歇的に腹痛が生じていたのがヒントになり、思いつきました。
グルタミンの説明サイト
まだ完調とはいきませんが、腹痛の程度も頻度も減っているようです。
夕食もきちんとしたものを食べまーす。
2021年10月11日
やる気がでないとき
疲れが溜まっていてどうもやる気がでない、ということがあると思います。
ーーどうしたら良いのか?
それを考えながらこのブログを書いています。
睡眠不足と頭の使いすぎでこのところかなりの疲労が溜まっています。
やる気がでないので、まずはストレッチから。ストレッチの途中で「あー、側坐核(脳の神経細胞が集まっているある部分です)って昨日ビデオが言ってたな」と思い出しました。そこでは、「まず動け」と。「動くことでドーパミンが出るから、やる気がでる。」と言っていました。動かないと何も起こらず、やる気もでないようです。
そこでネットで側坐核をひいてみました。Wikipediaによると
側坐核からは腹側淡蒼球、視床背内側核前頭前野に投射し、他に黒質、橋網様体(脚橋被蓋核など)へも投射する。
一方入力としては、前頭前野、扁桃体、海馬からのもの、扁桃体基底外側核のドーパミン細胞から中脳辺縁系を経て入力するもの、視床髄板内核、正中核からの入力があると記載がありました。
細かいところは調べないと分かりませんが、この入出力の感じだと、嗅覚と密接に関連しているようです。よし!交感神経刺激のためローズマリーだ!と思ったのですが手元にに見当たらず。。。どのように作用するか分からなかったのですが、自分が最も好きなパルマローザを嗅いでみました。そうすると、しばらくサボっていたブログを書くことができた、というわけです。どちらかというと、やる気がでたというよりは、やらない気が減った感じと思います。漢方薬でもやる気を後押しする処方がありますが、やらない気を除くような方法がないか、ちょっと考えてみようと思います。やる気が出てきたみたい(笑)
2021年06月18日
のぼせの季節
のぼせの症状を訴える人が多くなりました。
気温が上下することで、身体の熱が上へ上へと流れやすくなり、とくに過労時や不眠時にのぼせがひどくなります。
めまい、頭痛がのぼせたときの主な症状ですが、副鼻腔炎や中耳炎や耳鳴りも、のぼせで起こりやすくなります。
十分な休養が必要なことはもちろんですが、首の締まった服装やマフラーをいつまでも巻いているとかえってのぼせから炎症を起こしてしまいます。お気をつけください。
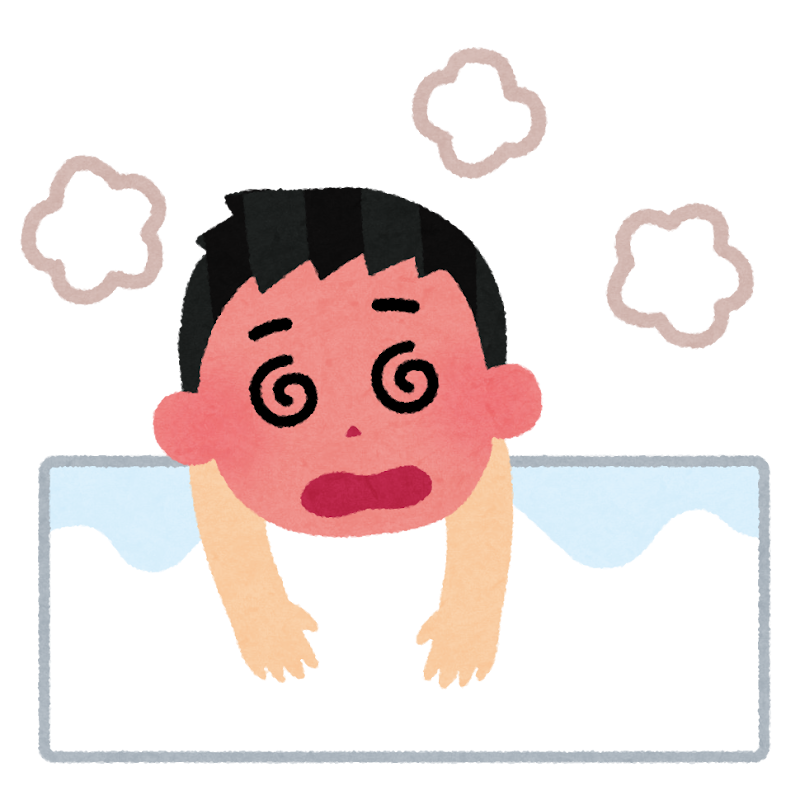
2021年03月29日
コロナ後遺症 2020年の総括
年末になりました。
コロナ後遺症が完治した方、まだ今一つの方、いろいろおられることと思いますが、来年も引き続き頑張っていきましょう。
治療の道筋が概ねできてきたので、一応開示しておきます。
コロナ後遺症は、PCR陽性でないにも関わらず症状が出ている方は特にですけれども、この病態の本質は過敏症だと感じます(陽性者には組織障害が残る人もいらっしゃいますが、治療方法はおおむね同じです。補陰(下記)の期間が少し長くなるかもしれません)。
受診された方たちは、食事内容の変更を私から言い渡されたことと思います。そして食事が良くなっても、日用品とか化粧品とか、電気とかwifiとか・・・改善点はたくさんあるものです(私の指導は、私が従来そういうことをしてきた経験に基づいています)。今まで大丈夫だったものに対しても過敏性が増してしまい、炎症が生じていることを認識する必要があります。
あとは漢方薬で炎症を除き、必要があれば解毒、その後に体液を満たして(これが補陰です)、さらに局所の炎症の処理をします。炎症はCRP値で判断されることが多いですが、フェリチン値で見るほうが分かりやすい印象です(ただしフェリチン値は様々な要因に左右されます)。また炎症の処理は通常の消炎鎮痛剤でだと効果が甘い印象があります(効くことはききますが)。
大体この時点で80%程度の症状がとれる方が多いです。
問題はあとの20%
この20%残っている方たちは、何かに反応するたびに症状がでてしまう方たちです。ここからは症状が出てしまった時に自分で対処できるようにしていく訓練の段階です。皆さん時々症状が戻ってしまい、私も指導に力が入ります。スパイスの有用性をこの段階では実感していただけると思います。スパイスを使用する理由は、薬で対応を続けると過敏になりすぎる懸念があること、スーパーで容易に入手できることです。症状がコントロールできるようになると、ずいぶん皆さん朗らかになってきます。
当然治ってくると、元の生活よりも内容がよくなる(良くないと治らないです)ので、健康度が増して終了となります。
来年はもっと高い健康を目指しましょう。
2020年12月28日
コロナ後遺症と食品添加物
コロナ後遺症で最近感じていることは、食品添加物を少なくすると改善していくということです。
先日、あるコロナ後遺症疑いの男性が「コンビニ弁当ばかり食べていたが、自炊するようになったら熱がだんだん下がってきた。」とおっしゃいました。それに伴って嗜好も変わるようで、治療を終了した方は、お菓子類やジャンクフードを食べなくなったという話をしておられました。
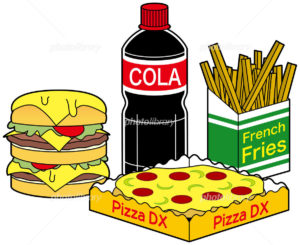
私は、食品添加物をはじめとして、身体に負荷のかかるものが口からまたは皮膚から入ることで全身に小さい炎症が生じていて、それがなくなると治るのではないかと考えています。
現在はそういう考え方に沿って、漢方薬と食事等の指導をしています。
2020年08月22日
コロナ感染の後遺症?
ずっと微熱が続く、ずっと経験したことのない頭痛を時折感じる、何だが息苦しいのが1カ月くらい続いている、などの症状を訴える人が増えているように感じます。大した事のない炎症といえばそれまでですが、どこの病院に行っても異常なしと言われる、と皆が口裏を合わせたように訴えてきます。これは何なのでしょうか?
コロナウイルス感染症が蔓延して久しいですが、どうもその後遺症のような風に感じています。
後遺症??そんなことを言っている情報番組はないけど・・?と思われるかもしれません。でもそういう番組に出てこられる先生方のところにかかられる患者さんは、軽症者の方は少ないのでしょう。
しかし私たちのような小さい診療所では、こういう症状の方を診察する機会が多いので、どうもこれはコロナウイルス感染の後で生じた、サイトカインストーム(過剰な免疫現象のことです)が何等かの理由で収まっていないのだなと推測することができます。実際、免疫を調整するように漢方薬を使ってみると、1カ月続いた症状が1-2日で取れてしまいます。しかしその後、数日して何かの刺激を受けたからなのか、少しだけ症状がでたり引っ込んだり。一直線には治りませんが、不安にならない程度の症状に落ち着いていきながら治っていくのです。「コロナウイルスに感染した覚えはない!」と皆さんおっしゃいますが、無症候性感染(症状がでない感染)でもサイトカインストームは起こりますので、決して不思議なことではないのです。
サイトによってはサイトカインストームに桂皮が有効、と書かれていることが多いですが、私はそうは思いません。一番確実にサイトカインストームを抑えてくれるのは恐らく甘草です。甘草+何か、ということで収まりをつけるのが有効でしょう。あとコロナウイルス感染予防に麻黄湯が有効ともいわれていますが、まあ否定はしませんが、あまり良い方法とも思いません。理由は割愛します。
今後はこういう患者さんが増えると思うので、今ある対策よりも、さらに良いものを考えておこうと思っています。

2020年05月08日
コロナ 原則だけでは通用しない?
食べ物でコロナウイルス感染を予防しよう!というサイトが散見される。
まあそれはそれでよいのだが、落とし穴があるように感じたので一応そのことを書いてみる。
邪が体表面に入ってくるのを抑えるのは、漢方の理論では発散性のある食べ物、紫蘇だったりネギだったりだろう。確かにそれで予防と言えるかもしれない。しかし、今回のコロナウイルスだが、邪が入ったことが分かりにくいという特徴がある。しかもその後に生じる反応は、自分で自分の細胞をやっつけるという反応である。これを制御するのに紫蘇やネギではどうなのか・・・?。
ウイルスが体内に入るまでは発散で予防としてはよいかもしれない。しかしウイルスが体内に入ったあとも発散性を強くしていくと、自分の細胞をやっつける作用を助長してしまう可能性があると考える。むしろ酸味のものを食べて、少し体のエネルギーの流れを内向きにして(収斂作用)、血管も引き締めて炎症をを抑えていく(血管透過性を抑制する)ようにするのが良いのではないだろうか?(そんなに効果があるのかどうか、やや疑問もあるが)そして今回のウイルスに関して思うのは、みな「詰まり感」がひどく出るので、体のエネルギーのめぐりを強くする作用(理気作用)が強いものが必要ということは間違いないところだろう。
私が見たのは薬膳研究家のサイトであったと思うが、ちょっと危うい感じがしたので、一応コメントしてみた次第。

2020年04月22日
季節が1か月早く進むので
季節が1か月早く進むということを経験したことがありません。
花粉症のピークも3月から2月に前倒し。
恐らくコロナウイルスも、気温の上昇とともに無くなっていくのではないでしょうか?
尊敬する根路銘先生の対談を読んで、なるほどと思いました。
花粉症も4月を待たずに収束の方向でしょうか??
ところが思わぬ気温の上昇で困ることがあります。気虚(エネルギー不足)です。
花が咲くように身体の気が緩み、いや!緩みすぎ、
身体から気が逃げてしまうような気虚を生じている方が多いように感じます。
疲れてもいないのに、エネルギーが失われている人が少なくありません。
そういう人は、花粉症でもないのにくしゃみがやたらでたりしてしまいます。
もしも自分もそうかな?と感じる人がいらっしゃったら、少し酸味のものを食べて、引き締めておきましょう。
もちろん漢方薬でも対応可能です。
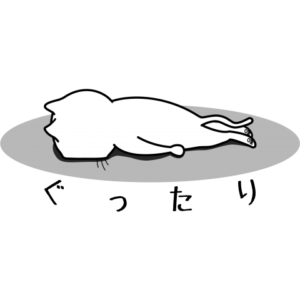
2020年02月26日
新型肺炎に関する見解
厚生労働省から新型肺炎に関する受診の目安が発表されました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200217/k10012289041000.html
不安を感じた人たちが検査を希望して殺到するようなことがないと良いのですが。何故なら、既に不顕性感染者(症状がなく感染する人)は多数存在するはずであり、大した症状でなくてもタイミングが悪いと感染者とされてしまう可能性もあります。ほとんどの人が重症肺炎になるような報道がなされていますが、それは違うのではないでしょうか。
対応する薬がないのは確かなので、高齢者、妊婦、免疫の状態が良くない人は、かなり注意深く人込みを避けるなどの配慮が必要と思われます。しかし、基本的に元気な人にとってはふつうか、ちょっと酷い風邪程度で収まるものであり、日頃から免疫が下がるようなことを避けることが必要でしょう。あとマスクをしていても、長時間の接触により感染は広がっていくと思われるため、何より人込みを避け、他者との不要不急の接触を避けることが重要だと思います。
新型インフルエンザのときもそうでしたが、ひと通りいきわたると収束してきます。もう数週間かなと思っています。ただし、船舶に残っている人たちの動向には左右されるかもしれませんが。
2020年02月18日